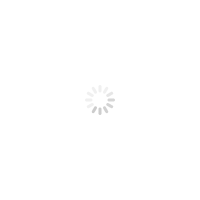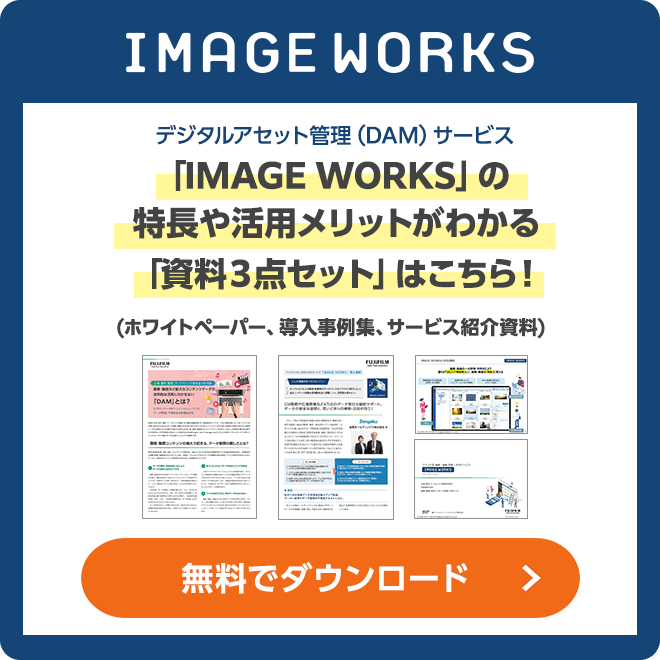- クラウド型ファイル管理・共有ならIMAGE WORKS
- お役立ち資料
- DAMが定着しない5つの原因と成功に導く実践的な対策
DAMが定着しない5つの原因と成功に導く実践的な対策
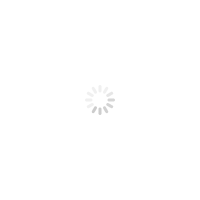
「DAM(Digital Asset Management:デジタルアセット管理)システムを導入したのに、ほとんど使われていない」「一部の部署だけが使っていて、全社展開できない」──このような悩みを抱えている企業は少なくありません。せっかく投資したDAMシステムが宝の持ち腐れになってしまうのは、導入企業にとって大きな損失です。
本記事では、DAMが社内で定着しない典型的な失敗パターンを分析し、成功に導くための実践的な対策をご紹介します。
目次
DAMとは?デジタルアセット管理の基本と重要性
DAMとは、企業が保有する画像、動画、ドキュメントなどのデジタルコンテンツデータを一元的に管理し、スムーズに活用するためのシステムです。単なるファイルサーバーとは異なり、データ一つひとつに対し、属性情報やタグなどのメタ情報を付与することにより、本来は検索がしにくい画像や動画、音声やデザインデータも、スムーズに検索することが可能になります。また、データへのアクセス・編集権限の細かな制御、データのバージョンや権利情報の管理といった機能を備えています。
なぜ今、企業にDAMが必要なのか
ビジネスにおいてもスマートフォンを中心とした容易な画像・動画の生成や、SNSでの発信などが進み、組織が扱うコンテンツデータは爆発的に増加しています。製品の画像、イラストや図版、設計図、ロゴ、プロモーションやSNS用の各種画像・動画、PDFや印刷物のデザインデータ、営業資料、各種コーポレート情報など、日々生み出されるデータは膨大です。これらを効率的に管理できなければ、以下のような問題が発生します。
- 必要なデータを探すのに時間がかかる
- 同じようなプロモーション素材を重複して制作してしまう
- 古いバージョンの動画を誤って使用してしまう
- 権利関係が不明確な素材を使用し訴訟に発展してしまう
- 発表前の製品画像と知らずに使用し、社外に情報が漏れてしまう
DAMを適切に導入・運用することで、これらの問題を解決し、業務効率化とガバナンス強化を同時に実現できます。検索時間の短縮、制作コストの削減、ブランド統一性の向上など、その効果は多岐にわたります。
ただし、これらの効果を得るためには、DAMを組織に定着させることが前提となります。
なぜDAMが社内で活用されないのか? 5つの典型的な失敗パターン
せっかくDAMを導入しても、その後の活用が社内で進まないというケースは珍しくありません。ここでは、よくある失敗パターンを5つに分類して解説します。
導入目的と効果測定が不明確
「とりあえずDAMを入れれば業務が改善するだろう」「画像の管理が便利になりそう」という曖昧な期待で導入してしまうケースです。各部門が抱える具体的な課題を把握せず、全社一律のシステムを押し付けてしまうと、現場からは「使う理由が分からない」という声が上がります。
また、具体的な目標の設定がなければ、現場での改善のPDCAも回せません。投資効果が見えず、経営層からの支援も得られなくなってしまいます。
運用ルールの不在と属人化
DAMは導入しただけでは機能しません。ファイルの命名規則、フォルダ構造、メタデータの付与ルールなど、運用の基本ルールが定まっていないと、すぐに混乱状態に陥ります。
「山田さんはこのフォルダに入れているけど、田中さんは別のフォルダを使っている」「同じ商品画像なのに、人によってファイル名が違う」といった状況では、せっかくのDAMも単なる「整理されていないファイルサーバー」になってしまいます。さらに、キーパーソンが異動や退職をすると、運用そのものが停滞してしまうリスクもあります。
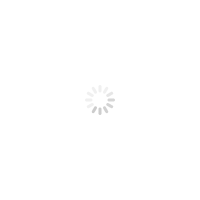
社内浸透施策の不足
多くの企業では、DAM導入時に使用方法を1回案内して終わり、というケースが見られます。しかし、新しいシステムを定着させるには、継続的な啓発活動が不可欠です。
使い方が分からない、メリットを実感できない、という状態のまま放置されると、ユーザーは徐々に離れていきます。特に、ITツールに不慣れな社員にとっては、最初のハードルを越えることすら困難です。定期的な説明会の開催、マニュアル・Q&Aの整備、成功事例の共有など、きめ細かなフォローが必要です。
システムと現場ニーズのミスマッチ
「高機能なDAMを導入したのに使われない」という場合、多くはシステムと現場のニーズがずれています。例えば、マーケティング部門は高度な画像検索機能を求めているのに、キーワード検索しかできない。デザイン部門は大容量ファイルの高速プレビューが必要なのに、サムネイル表示が遅い、といった具合です。
また、UIが複雑すぎて日常的に使うには負担が大きい、モバイルに対応していないため外出先で使えない、といった利便性の問題も活用を妨げる大きな要因となり、DAMの定着を阻害します。
組織文化・業務フローとの不整合
DAMの活用には、既存の業務フローの見直しが必要になることがあります。しかし、「今までのやり方を変えたくない」という抵抗や、部門間の縦割り意識が強い組織では、新しいシステムの浸透は困難です。
例えば、営業部門は独自のファイルサーバーを使い続け、マーケティング部門だけがDAMを使っているような状況では、全社的な情報共有は実現できません。トップダウンでの推進力が弱く、各部門の自主性に任せきりでは、組織全体での活用は進みません。
DAMを定着させるための実践的な対策
失敗パターンを踏まえた上で、DAMを社内に定着させるための具体的な対策を解説します。これらの対策を組み合わせることで、DAMの活用率は着実に向上していきます。
対策1 明確な目的設定とKPI管理
まず重要なのは、DAM導入の目的を明確にすることです。「なぜDAMが必要なのか」「どんな課題を解決したいのか」を、部門ごとに具体的に洗い出します。
営業部門なら「提案資料作成時間を20%削減」、マーケティング部門なら「キャンペーン素材の再利用率を50%向上」、多拠点を持つ企業なら「拠点間の画像共有により新規撮影費10%削減」など、測定可能な目標を設定します。そして、これらのKPIを定期的にモニタリングし、改善につなげていくことが重要です。
対策2 運用ルールとガイドラインの策定
DAMを「誰でも使える状態」にするには、明確なルールが必要です。以下のような項目を含むガイドラインを作成し、全社で共有しましょう。
- ファイル命名規則(例:「商品コード_用途_作成日」「作成日_部門_ファイル内容」)
- フォルダ構造の標準化
- ファイルの属性情報の定義
- アクセス権限の設定基準
- 承認フローのルール
ちなみに属性情報とは、ファイルに付与するデータのこと。例えば商品画像であれば、「商品名・商品コード」「撮影日・使用期限」「カテゴリー(製品写真、イメージ写真、使用シーンなど)」「使用可能範囲(Web用、印刷用、社内限定)」などが該当します。これらの属性情報を設定することで、より高度な素材管理が可能になります。
大切なのは、現場の意見を取り入れながらルールを作ることです。机上の空論ではなく、実務に即した実用的なルールでなければ定着しません。
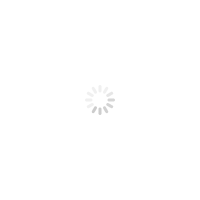
対策3 スモールスタートと段階的展開
いきなり全社展開するのではなく、まずは意欲的な部門やチームから始める「スモールスタート」が効果的です。パイロット運用で成功事例を作り、その効果を実証してから他部門に展開していきます。
例えば、最初はマーケティング部門の商品画像管理から始め、効果が確認できたら営業部の営業資料、広報部の社内広報資料……というふうに段階的に対象を広げていく進め方です。小さな成功を積み重ねることで、組織全体の理解と協力を得やすくなります。
対策4 アンバサダー制度による横展開
各部門にDAMの推進役となる「アンバサダー」を任命し、現場レベルでの浸透を図るといった対策もあります。アンバサダーは、部門内での質問対応、活用事例の収集、本部へのフィードバックなどの役割を担います。
IT部門だけで推進するのではなく、各部門のキーパーソンを巻き込むことで、より実務に即した活用が進み、DAMの定着が加速します。アンバサダー同士の情報交換会を定期的に開催し、ベストプラクティスを共有することも効果的です。
対策5 定期的な効果測定とPDCA
DAMがきちんと使われているかを定期的にチェックし、改善していくことが大切です。といっても、難しく考える必要はありません。まずはユーザーの声を聞いてみましょう。身近なメンバーに「使ってみてどう?」と聞いてみるだけでも、貴重な改善のヒントが得られます。そして、例えば「特定の検索キーワードで見つからない」という声があれば、ファイルの登録方法を見直すといった改善を行います。
客観的なデータから分析することも有効な対策です。例えば月に1回、「先月より利用者は増えているか」「どの部門がよく使っているか」など、システムが自動的に記録している基本的なデータを確認します。そして特定の部門だけ利用率が低ければ、その部門特有の課題を確認する、といった具合です。数カ月に一度でも構わないので、定期的に振り返る習慣をつけることが大切です。
対策6 成功事例の共有と改善
DAMを活用して業務改善に成功した事例を積極的に社内で共有します。「○○部門では、DAM導入により画像検索時間が70%削減された」「重複制作がなくなり、年間○○万円のコスト削減を実現」といった具体的な成果を示すことで、他部門のモチベーションも高まります。
そして社内報、イントラネット、定例会議など、さまざまなチャネルを活用してこの成功事例を発信します。また、うまくいかなかった事例からも学び、同じ失敗を繰り返さないよう改善につなげることが大切です。
業務効率化とガバナンス強化を実現するDAMサービス「IMAGE WORKS」
DAMの導入・定着には、適切なシステム選定と運用設計が不可欠です。富士フイルムの「IMAGE WORKS」は、2,500社以上の導入実績を持つ、信頼性の高いDAMサービスです。
データへの100以上の属性情報付与やCSVでの一括付与、AIを活用した画像検索などの高度な検索性、直感的で誰でもスムーズに使えるUI、モバイル対応による場所を選ばない利用環境など、現場のニーズに応える機能を豊富に搭載し、ご好評をいただいています。さらに、ダウンロード申請・承認機能※1によるガバナンス強化、コンテンツ提供サイト機能※1による社内外への効率的な共有など、運用面でのサポートも充実しています。
専任のカスタマーサクセスチームが、導入から定着まで伴走支援。貴社の課題に合わせた最適な運用設計のご提案にも対応いたします※2。DAMの導入・活用でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
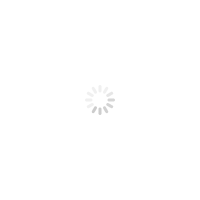
※1 オプション機能です。
※2 一部有償対応になる場合もございます。
IMAGE WORKSについて
さらに詳しい資料セットはこちら