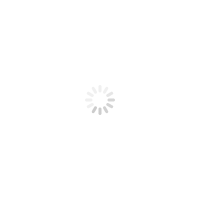- クラウド型 ファイル送受信サービス SECURE DELIVER
- お役立ち資料
- 社外・社内で使える5つのデータ共有方法のメリット・デメリットを解説
社外・社内で使える5つのデータ共有方法の
メリット・デメリットを解説
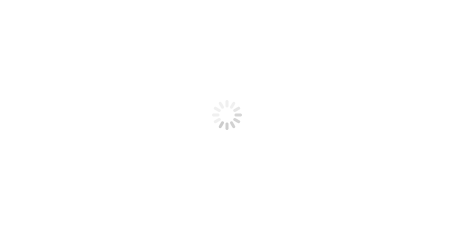
リモートワークが定着するに伴い、企業におけるデータ・ファイル共有の機会が増えています。
しかし、安全性が不十分だと機密データ漏えいやコンプライアンス違反につながるリスクがあります。
本記事では、データ共有のリスクと安全にデータを共有するための方法と適切なツールを選ぶためのポイントを解説します。
目次
データ・ファイル共有に潜むリスク
データ・ファイル共有には、機密データの漏えいやコンプライアンス違反などのリスクが潜んでいます。適切な対策を怠れば、企業に甚大な損害が及ぶ可能性があります。具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
機密データ漏えいのリスク
個人情報をはじめとする企業内のデータ保有・送受信量が増大し、データ・ファイル共有におけるちょっとしたミスや故意により、機密データが漏えいするリスクは高まっています。リモートワークの普及で社外からのデータ共有が増え、近年このリスクはますます見逃せないものになりました。
企業が保有する機密情報が外部に漏れてしまうと、競争力の低下や企業イメージの失墜、さらには多額の損害賠償につながるリスクがあります。特に個人情報や技術情報、営業秘密などの重要データが漏えいした場合、その影響は甚大です。個人情報が漏えいすれば、企業は高額な賠償金を支払う必要が生じることもあります。また、信用失墜による事業への影響は避けられず、存続が危ぶまれる状況になることもあるでしょう。
コンプライアンス違反リスク
安全性を十分に確保しないままデータを共有すると、コンプライアンスに違反するリスクも発生します。個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)など、データ取り扱いに関する法令やルールに違反してしまう可能性があり、その結果、法的処分や高額な過料を科される恐れがあります。さらには企業の信用失墜やブランドイメージの低下など、事業に深刻な影響を与えかねません。
無料のメールやファイル転送サービスを利用するリスク
ファイル共有のために無料のサービスを使う行為は、とりわけリスクが高いといえます。例えば無料メールサービスはセキュリティ対策が不十分であることが多く、第三者に傍受される恐れがあります。また無料のファイル転送サービス(ファイル共有サービス)も、データ保管場所やアクセス制御が不明確なケースが多く、情報漏えいリスクが高くなります。つまり秘密保持契約を結んでいないサービスにビジネス用のデータを預けることであり、自社のセキュリティ意識を問われかねません。特に重要なデータの共有に使うのは控えたほうがよいでしょう。
また、無料サービスのページはさまざまな広告を掲出している場合が多く、その広告内容で相手の心証を損ねたり、相手が誤って広告をクリックし、不審なサイトへの誘導やファイルのダウンロードにつながったりするリスクがあります。
共有方法1:メール添付でデータを共有する
データ共有を実現するための具体的な5つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。まずはメール添付でデータ共有を行う方法です。この方法には、以下のメリット・デメリットがあります。
メリットコストがかからず簡単に利用可能
メール添付によるデータ共有は、メールクライアントやWebメールさえあれば誰でも利用できます。新たなツールやサービスを契約する必要がないため、コストをかけずに簡単に利用が可能です。多くの企業や個人がすでに業務でメールを活用していることから、違和感なく運用を開始できます。
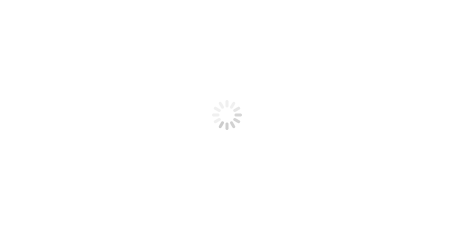
デメリットセキュリティリスクと容量制限
メール添付によるデータ共有には、いくつかのセキュリティ上の懸念があります。まず、情報漏えいのリスクが存在します。ヒューマンエラーにより、誤った宛先に送信されてしまう可能性があるからです。また、相手に届くまでのメール通信経路の中に暗号化されていない部分があれば、第三者に傍受される恐れがあります。機密ファイルをメールで送受信するのは避けたほうがよいでしょう。セキュリティを重視する相手企業からは、メール添付によるデータの受け渡しを拒否されることもあります。
さらに、大容量データをメールで送信しようとすると、ファイルサイズの制限や回線の帯域制限にひっかかり、送信できない場合があります。
共有方法2:クラウドストレージを使ってデータを共有する
クラウドストレージ(オンラインストレージ)を使ってデータを共有する方法には、以下のメリット・デメリットがあります。
メリット大容量データの共有や編集が簡単
クラウドストレージは、数百MBや数GBの大容量ファイルでもスムーズに共有できるのがメリットです。格納先のURLを相手に案内してデータを共有するため、URLを無効化することなどにより、メール添付でのデータ共有と比べ誤送信のリスクを抑えることができます。また、特定の相手と継続的にファイルを共有・編集する用途に向いています。
有料のクラウドストレージを利用すれば、ファイルやフォルダへのアクセスレベルを詳細に設定できる場合が多く、情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。例えば「閲覧のみ」「アップロードのみ」「編集可」など複数段階のアクセスレベルを指定できます。また、アクセスログを確認することで、いつ誰がファイルを閲覧・編集したかを追跡可能な機能もあり、監査の際に有用です。
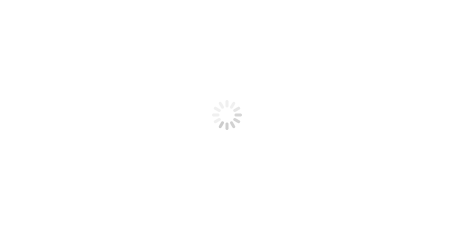
デメリットコストの発生、使い勝手に難あり
ビジネス向けのクラウドストレージはサブスクリプション型のサービスがほとんどで、ストレージ容量や機能に応じて利用料金が発生します。特に大容量のデータを保存する場合は、高額な料金がかかる可能性があります。初期導入費用と運用費用の双方を考慮する必要があるため、経費的に負担となることも考えられます。
また、データ共有という単純な用途においては、メールよりも使い勝手が劣る側面もあります。共有したいファイルをクラウドストレージにアップロードし、共有リンクを設定してメールで送付するという手順が必要になるためです。
加えて、フォルダ管理やアクセス権限設定、バージョン管理、共同編集などの高度な機能を利用する際に、操作ミスが起こる可能性があります。ITリテラシーに不安がある方にとっては、複雑な印象を受ける場合もあるでしょう。
共有方法3:チャットツールでデータを共有する
チャットツールでデータを共有する場合、以下のメリット・デメリットがあります。
メリットリアルタイムでのやり取りが可能
チャットツールを使えば、データ共有時にリアルタイムのやり取りが可能です。添付ファイルに関する質疑応答をその場でスムーズに行え、スピーディーな業務連携が図れます。特に遠隔地間でのデータ共有の際に効果的で、いちいちメールを行き来させる手間が省けます。重要な案件資料のレビューなどにも活用でき、議論しながら直接ファイルを修正・確認するといった同期作業が可能です。
デメリットファイル履歴管理の手間と容量制限
一方で、チャットツールではファイル履歴の管理に手間がかかります。チャット画面上でデータ共有の履歴をさかのぼることは可能ですが、「誰がどのファイルを最終的に受け取ったのか」がわかりづらい面があります。加えて、チャットツールは検索性や一覧性に乏しく、過去ログから目的のファイルを探し出す作業も面倒です。
さらに、チャットツールの多くにはファイル添付の容量制限があり、大容量データの共有が困難です。そのため、クラウドストレージサービスと組み合わせてファイルを共有しているケースも多いといえます。
共有方法4:USBメモリでデータを共有する
USBメモリを使ってデータを共有する方法には、以下のメリット・デメリットがあります。
メリット持ち運びが便利
USBメモリはコンパクトで携帯性に優れているため、手軽にデータを持ち運べます。PCにUSBメモリを挿し込むだけで簡単にファイルを保存・閲覧できるため、使いやすさも魅力的です。特に大容量データを社内外で共有する必要がある場合に、便利なツールといえます。
デメリットセキュリティリスクの高さ
一方で、USBメモリを使ったデータ共有にはセキュリティ上の重大なリスクがあります。USBメモリの紛失や盗難に遭うと、その中のデータが漏えいする恐れがあるからです。また、ウイルスに感染したUSBメモリを使用すれば、企業のシステムや情報資産に被害が及ぶ可能性もあります。
加えて、USBメモリ上のデータを適切に管理することは難しく、アクセス権限の設定や監査証跡の確保が行えません。コンプライアンス上の課題が多数あるため、企業によっては全面的にUSBメモリの業務利用を禁止している場合もあります。
共有方法5:ファイル転送サービスでデータを共有する
ファイル転送サービス(ファイル共有サービス)でデータを共有する場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット大容量データも安全・簡単に送付可能
有料のファイル転送サービスを利用すれば、数百MBや数GBの大容量データでも安全に送受信できます。転送中の通信経路が暗号化されており、共有するデータにパスワードをかけて安全性を確保できるサービスもあるので、セキュリティの問題も解決できます。共有ファイルへのリンクをメールで送るサービスであれば、添付ファイル制限を気にすることなく、大容量の動画やCADなどのデータも手軽に共有できます。
なお、多くのサービスではファイル受け渡し時の追跡が可能で、誰がどのファイルを受領したかをしっかり確認できます。監査対応でも有用な機能です。
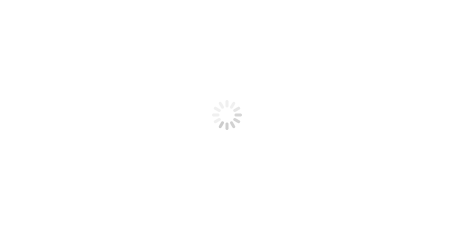
デメリットサービスにより機能やコストに大きな差異
また、ファイル転送サービスにもいろいろあり、利便性、セキュリティレベル、価格帯、操作性などが異なります。企業の状況や課題にそぐわないサービスを選んでしまうと、必要な機能が不足する、コストが高すぎる、使い勝手が悪いなどの問題が生じてしまいます。
サービスによって料金体系もさまざまなので、自社の利用状況を調査した上でプランを選ぶことも重要です。機能が過剰であったり企業規模に見合わないサービスを選ぶと、高額な費用が発生する可能性があります。例えば転送データ量に応じた従量課金制のサービスもあれば、IDごとに課金するタイプのサービスもあります。後者の場合、ユーザー数が増えるほど利用料がかさみます。さらに、高度なセキュリティ機能を求めれば、オプションの有料プランに加入する必要があるかもしれません。
自社に合った安全なデータ共有方法の選び方とは?
では、安全かつ効率的なデータ共有を実現するにはどうすればいいのでしょうか。サービスの選定・導入に当たって以下の点を十分に検討する必要があります。
取り扱うデータの重要度やサイズを正しく把握する
機密データなのか一般的なデータなのか、大容量データが多いのか少ないのかによって、求められるセキュリティレベルや適切なツールは変わってきます。自社のデータ状況を正確に把握することが大前提となります。
業務プロセスとデータ共有の現状を確認する
機密データを社外へ送付する業務があれば、専門のファイル転送サービスを利用する必要があります。一般的な社内資料の共有ならグループウエアやクラウドストレージでも可能です。現場でどのようにデータ共有が行われているのかを把握し、業務実態に合ったツールを選定しましょう。
セキュリティ機能を入念にチェックする
ファイル暗号化、多要素認証、アクセスログの確認機能、送信取り消し機能など、自社のセキュリティポリシーを満たす機能が搭載されているかを確認しましょう。サービス提供事業者のISMSやPマークなどの取得状況、サーバーが管理されているデータセンターのセキュリティ水準も確認しておきましょう。
ユーザビリティと操作性の良さを確かめる
直感的な操作が可能か、画面デザインはわかりやすいか、共有までの手順はシンプルかなど、実際に使うユーザーにとって、本当に操作性がいいかどうかを確認する必要があります。操作が複雑で使いづらいと、定着に時間がかかったり誤操作が発生したりする可能性があります。導入前にトライアル版で操作性を確かめてみるべきでしょう。
ファイル受け取り側の環境と、相互運用性を事前に確認する
ファイルの受け取り側がどのツールを使っているかによって適切な共有方法は変わります。機密データ共有相手の中には、「無料ツール不可」とする企業もあるでしょう。事前にヒアリングして、双方で利用可能なツールかを見極めましょう。
データ共有の安全性を高めるポイント
安全かつ効率的なデータ共有を実現するためのポイントは以下のとおりです。
アクセス権限の適切な設定
データを共有する際は、必要最小限の権限のみをユーザーに付与することが重要です。アクセス権を適切に設定していないと、意図せずデータが漏れる可能性があります。アクセス権限を細かく設定でき、ログ管理機能があるサービスを選ぶことで、安全性を高められます。
セキュリティポリシー・従業員教育の徹底
ツールを導入する際は、セキュリティポリシーの徹底が欠かせません。データ取り扱いのルール策定、従業員教育の実施、運用監視の体制整備など、さまざまな対策が求められます。またシステム側の対策だけでなく、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることも重要です。パスワードの管理、共有ルールの徹底、各データが漏えいした際の影響度について理解を深めさせるなどのセキュリティ教育を行い、意識改革を促すことが不可欠です。
統制と監査対応の強化
共有データへのアクセスログや送受信記録を障害発生時まで保持し、追跡・監査が可能となる仕組みを構築しましょう。データ共有における可視性を高め、不正リスクを抑制することが重要です。
まとめ
社内外へのデータ共有方法は多数あり、それぞれにメリットとデメリットがあります。特に社外向けについては、安全で効率的なデータ共有を実現するために、ツール導入前の十分な検討と、適切な運用が不可欠となります。
富士フイルムの法人向けクラウド型ファイル転送サービス「SECURE DELIVER(セキュアデリバー)」は、ファイル転送に特化したシンプルな機能で、誰でも簡単に操作できることで誤操作を抑え、安全なデータ共有が行えます。ファイルの暗号化やウイルスチェック、ファイルの自動削除、各種ログの記録といったセキュリティ対策に加え、上長等によるファイル送信承認などのガバナンス機能も充実。送付先ユーザーのファイル取得状況をいつでも確認できるため安心して利用でき、従量課金制を採用しているためローコストでの全社導入も可能です。機密データの安全な送受信や、大容量データの手軽な共有などにおすすめです。
「SECURE DELIVER」に興味がありましたら、まずは無料体験版をお試しください。資料請求・お問い合わせもお待ちしております。
SECURE DELIVERについて
さらに詳しい資料セットはこちら